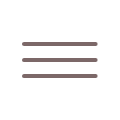厳かに、慎ましやかな
大和のハロウィン。

和ロウィンとは
- WALLOWEEN -
- WALLOWEEN -

和ロウィンは、和の歴史・文化にふれることで「知らないを知ろう」という考えのもとスタートした活動です。
「和の文化」を皆で体験・学び合うことで。街の地域活性化に繋がるよう応援します。
「和の文化」を皆で体験・学び合うことで。街の地域活性化に繋がるよう応援します。
私たちについて
- ABOUT US -
- ABOUT US -

和ロウィンを運営する「実行委員会」
私たち「和ロウィン実行委員会」は、企画から打ち合わせ・会場設置ほか、和ロウィンに関わる業務を管理する運営団体です。
お知らせ
- NEWS -
- NEWS -
令和7年10月11日
令和7年度 和ロウィンシーズンがスタートしました。
令和6年10月31日
令和6年度 和ロウィンが東大和市駅前のBURGCAMPで開催されました。
令和6年10月12日
令和6年度 和ロウィンシーズンがスタートしました。
令和6年8月12日
令靖国神社ツアーを開催しました。遊就館に訪れ、沢山の歴史に触れました。
令和6年4月29日
東京都立川市の国営昭和記念館を訪れました。
令和5年10月31日
第一回目の和ロウィン 令和5年度 和ロウィンが東大和市駅前で開催されました。
支援団体
- SUPPORT -
- SUPPORT -

共に「和」を広げていく仲間たち
令和7年度 協力店舗
----------------------------------------------
やきとり処 忠歩
SUNDAYS
オイスターバル WoodCamp
Café de Nostalgy(カフェ デ ノスタルジー)
パン焼き小屋もくもく
〜 他店は順次掲載中です 〜
令和5年度・6年度 協力店舗
----------------------------------------------
カフェ デ ノスタルジー[café de Nostalgy]
駄菓子らんど 華屋
パン焼き小屋もくもく
ぐらばぁ亭
生そば 大むら
やきとり処 忠歩
BIGBOX東大和
SUNDAYS
家庭料理いざかや ちどり
オイスターバル WoodCamp